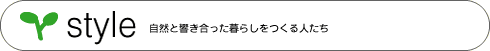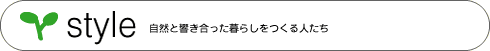|
「コモン・センス」01/10/29
なぜか私は都会を避けるような生き方をしてきました。東京の大手企業に入社できることになりながら辞退し、京都の自宅から通えるところに就職しました。そこではNYへの駐在や留学の声をかけられましたが、躊躇することなく断っています。私は工業文明国の大都会がなぜか不安だったのです。それは生い立ちと関係がありそうです。
1944年、私は5歳の時に西宮から都市爆撃を避けて、母に手を引かれて京都の町外れに疎開しました。すぐに14人いた村の子どもと交わり、毎日のように秋の野山を駆けめぐるようになりました。野苺や山栗をとったり椎やムクの実を拾ったりして食べるためです。その時の新鮮な気持ちは今も忘れられず、鮮明に記憶しています。
亡き母によりますと、それまでの私は母が隠したお菓子を母の目を盗んでは上手に見つけ出して食べ、後で叱られる毎日であったようです。ところが、突然、誰にも叱られずに、しかも初めて口にする自然の恵みを自分の目で見つけて採り、独自の判断力をたよりに食べることになったわけです。蜂の子も飲み込みました。
ガキ大将が雀蜂の巣を見つけると、長い竹の先にナスを突き刺し、そのナスを焚き火で焼き、焼いたナスで巣をつついて採るのです。なぜか蜂は、遠くで竹を操る人間ではなく目先の熱いナスを攻撃し、次々とお陀仏になっていました。不思議でした。
こうした体験は、面白かったとか怖かったでもなく、美味しかったとか腹がふくれたとかでもなく、独立心を目覚めさせたのです。母といえども理不尽な叱り方をすれば、「家を飛び出し、一人で生きていってやる」といった気概のようなものを5歳の時に身に着けました。あの解放感や自信は今も忘れられません。また、ものごとを突き詰めて考える癖も身につきました。たとえば、ぶん殴られるとその拳を恨むのではなく殴った人の意図に目を向ける。さらに、爆撃されても、恐ろしい爆弾を落とした人やその意図だけでなく、落とされる立場に誘った人やその経緯も明らかにしたくなる、など。
だから、翌年の春、居候をしていた家主の叔母に連れられた山菜とりを忘れられません。山菜の採り方を学んだ。たとえばタラの芽。2度目の芽までは採ってよいが3度目に出た芽は採るなと教えられた。タラの木が枯れてしまうから、と。子どもなりに得心しました。ゼンマイは、芽を3本は残して採れ、さもないと株が死に絶え、翌年の春は採れない、と。こうした教えを母も忠実に守っていましたが、それは「村の掟」や叔母への忠誠でした。子どもの私には、母のこの忠誠と叔母の教えとの間には何か決定的な差異があるように感じました。今にして思えば、叔母は時代や権力などがいかように変わろうとも常に変わらぬ「不易」を諭そうとしていたに違いない、と思います。叔母は、今を生きるための山菜の収穫も大切だが、明日も生き続けさせる野や山を守る方がもっと大事だと教えていたのでしょう。当時は誰しも飢えていましたが村人はこれを守っていました。
ある縁で、その後学生生活最初の夏休みを東京で過ごすことになりました。終生忘れられない恩人の家で過ごす機会でした。その間に突発自体が生じて山形県の山奥に足を伸ばしました。こうした体験を通して、都会への憧れが不安に変わり、やがては疑問になってしまったようです。都会に住むと、ゼンマイや雀蜂との付き合い方などのセンス、不易のセンス、コモン・センスを身に着けにくそうに思ったのです。
後日、レイチェル・カーソンは幼児期に自然と親しみセンス・オブ・ワンダーを触発する大切さを訴えました。納得しました。
|
|
アイトワの庭に出たキノコ。カニの爪のような形と色で臭いもカニの腐った様な臭いでした。
過去40年ほどの間に2度出たのを見つけました。
これが一度目の写真です。その時はたった一つでしたが、その翌年(1994)はこれより小さいのがたくさん出ました。
キノコ研究家によればサンコタケだそうです。
|
桜の木で見つけた虫。アブラムシでしょうか?
この赤いのは突然変異かもしれません。何故か女王のように見えました。
黒いのだけならかつて見ていたような気がします。 |
 |
|
|
レーチェルカーソンのザ・センス・オブ・ワンダーより (出版 ザ・ネーチャーカンパニー)
|
| 妻の人形教室展でも自然の豊かさや不思議さから学んだセンスをテーマにすることもあるようです。今年の春にテーマ”愛と環”のもとに開催した一場面です。 |
 |
|