|

|
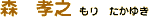

●アイトワのホームページ
●アイトワ循環図 |
|
自然、創造、悪循環
11/09/11
スモモのケムシを退治するうえで絶好の時期が終わり、モクレンの実がポトポトと落ちる時期を迎えました。スモモのケムシは、おびただしい数の幼虫がかたまっている間に気付き、退治すると簡単です。その適期が終わったわけです。落ち始めたモクレンの実は、「無から有」を生じさせる自然は「2つと同じモノをつくらない」ことに気付かせ、それは「作る」や「造る」とは異なり、「創る」の次元、「創造」だと気づかせます。
もちろんスモモのケムシは、かたまっている時点で退治しなくても、殺虫剤散布という楽な手があります。しかしわが家では、その手は原則として用いません。それは悪循環の始まりのように思われるからです。ケムシも小鳥の餌になる分ぐらいは見落としたほうが良さそうに思われます。その一環で、アシナガバチも退治しなかったのですが、先週はその巣で、恐ろしげなことが生じたわけです。でもそれは生態系の正常な姿でしょう。
屋内でも、とりわけ風呂場とLDK式の居間では、クモやムカデが縄張りを主張します。とりわけ風呂に入るときはムカデに要注意です。まず、長い柄のついたタワシにからませ、窓から放り出してから湯船に浸かります。決して殺しはしません、クモは噛みませんから追い出さずに、好きにさせています。原始的な生活だと思われそうですが、こうした生き方が健康の根本だとカラダで得心しているからです。もちろんココロの健康にとっては不可欠の要件ではないでしょうか。もちろん妻は、この考え方に当初は否定的でしたが、クモやムカデがゴキブリハンターだと知ったときに覚醒し、今に至っています。
庭には、さまざまな草木を茂らせています。そこには昆虫などさまざまな生き物が潜んでおり、毎年のように新発見がつづきます。こうした環境が、いつしか妻に「自然にはかなわない」という口癖をつくらせました。その形、枝のように化けたり死んだふりをしたりする技、色、彩り、環境に合わせた変色、あるいは悪臭を振りまいたり刺したり噛んだり尾を切り捨てたりする生き延び方。これらに感動するたびに自然の不思議さや偉大さに驚かされ、妻は創造力を掻き立てられ、創造的な生き方に切り替え始めています。
同時に、相対的な豊かさ、たとえば他の人より高価なものを持っているといったような豊かさにたいする興味が減退し、より絶対的な豊かさに憧れ始めています。思いもかけない虫や何年ぶりかで姿を見せた動物、それらを育んでいる美しい空気や水など、孫や曾孫の世代とも共感できそうな豊かさの方に、次第に興味が移って行ったわけです。
私は古稀を3年前に済ませましたし、妻も還暦を済ませています。おたがいに疲れを覚えやすくなっていますが、ゴロゴロした過ごし方をする気分にはなれません。自然の営みに囲まれていると、意欲や気力、さらには想像力や創造力を掻き立てられるからです。それが近代の悪循環の渦に巻き込まれずに済ませる秘訣ではないでしょうか。
この悪循環の好例は、近代医療に見いだせそうです。西洋医学に基づく健康管理法や医療機器の発達が、世界に例を見ない「人間ドック『健常』は8.4%」という現実をつくらせ、ココロの疾患者を急増させてきたのではないでしょうか。もちろん私も、近代医療の世話にはなります。しかしそれは同時に反省の時です。目に見えたり医療機器に教えられたりする悪現象が顕になるまで気づけなかったわけですから、それは反省の時です。その悪現象を生じさせた根本原因に気づき、その原因を取り除こうとせずに、顕になった悪現象に振り回されたことに対する反省の時です。
|
 |
スモモの葉に、卵からかえって間なしのケムシがかたまっている間に見つけ、退治しておかないと大変なことになります。無数のケムシがスモモの木の葉という葉に散らばってからでは手に負えません。ケムシを食べに来る常連の小鳥の数ではまにあわず、丸裸の木にされてしまいます。 |
|
 |
この時期にモクレンの実がポトポト落ち始めます。とりわけこの実が落ちはじめる初期は、誰の目にも自然は2つと同じものをつくらないことに気づかせます。モクレンは1つの実に、数10ないしは100ほどの種を結びうる花をつけますが、初期に落ちる実は、受粉率が悪く、1つとか2つ程度しか種を結んでいないのが常です。 |
|
 |
 |
 |
このハチの巣で、先週の水曜日の夕刻から木曜日の朝までの間に、凄まじい争いがあったわけです。なぜジュズダマランが切り落とされたのか。それはスズメバチが切り取ったのか。数十匹はいたアシナガバチはどうなったのか、瀕死の2匹を残し、その亡骸はありませんでした。 |
|
 |
ニホンミツバチの巣箱の入り口には、念にためにスズメバチがくぐり通れないように網をかけています。ニホンミツバチはスズメバチに巣を襲われると、多くの犠牲を出すようですがスズメバチを撃退できるそうです。セイヨウミツバチはそれができません。なぜアシナガバチはセイヨウミツバチと同様にスズメバチのなすがままになったのでしょうか。 |
|
 |
先週金曜日の夜に確かめたアシナガバチの巣。この巣で総計400匹ものハチが育っていたことになります。スズメバチに襲われた時点では、きっと巣穴に200匹以上の幼虫がいたことでしょうか。白い蓋を破られた巣穴の数に、破られたに違いないと思われる巣穴の数を加えると、半分近くを占めています。幼虫が生き残っていた巣穴は6つでした。私が殺したスズメバチは、この6匹を狙っていたのでしょう。 |
|
 |
ゴキブリを捕まえたクモ。 |
|
 |
 |
 |
1週間後のスモモのケムシ。枝を切り取った時の衝撃で、忍者のように分散しました。切り取った枝をじょうずに手元まで運べましたが、途中で他の枝に絡めたりしていたら、多くのケムシに逃げられていたことでしょう。この枝を見つけて切り取っていなかったら、明日にでも幼虫はスモモの木のあちらこちらに分散していたことでしょう。 |
|
|