|

|
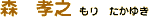

●アイトワのホームページ
●アイトワ循環図 |
|
トルコと日本人の真心
11/09/25
2度目のトルコ旅行は首都アンカラ(トルコ中部にある)から始まり、カッパドキアに立ち寄ったあとは方向を西に転じ、観光の合間に2箇所でトルコとの友好活動を重ね、最後はイスタンブールでした。この旅では民間人の国際交流の大切さを思い知らされ、過日(本年8月21日の当週記で)触れたセブンイレブンでの台湾の義援金を思い出しました。また、トルコの農業にも興味を惹かれており、前回の東トルコ巡りを反芻しています。
また記憶と記録の差異に仰天させられました。それはブルーモスクを訪れた日のエピソードです。実は、朝食時に、その柱の太さは「大人3人では取り囲めそうにない」と前回の記憶をたどって語り、東大寺の大柱よりはるかに太いと言って怪訝な顔をされました。現実はその比ではなかったのです。これが今回の旅で得た1つの教訓です。
トルコでは今も、120年前の紀伊半島沖で座礁したトルコ軍艦の水兵に、地元民間人がしめした誠意が語り継がれています。その真心に対するお返しにとばかりに、第一次湾岸戦争の際に、大勢の日本人がイラクに取り残されていると知ったトルコは急遽臨時便を仕立て、飛行機で救出しています。その後、1998年のトルコ大地震の時に、いち早く駆けつけた日本の救援隊や義援金が今もかたりぐさになっています。このたびの東日本大震災では、トルコはいち早くお返しをしてくれましたが、議会では黙祷もしていますし、3千数百あるモスクではそろって日本の復興祈願をしています。また、トルコでは毎日いたるところで国旗などが掲げられていますが、その旗がすべて半旗になっていたとか。「あのような光景を見たのはその時だけ」とトルコ人年配者に聞かされました。
その直後に、アメリカが911後のテロ対策として軍事行動に出ましたが、莫大な予算をさき、兵士(国民)に多大な犠牲にしいながら、未来世代に苦労の種を背負わせただけに終わりそうと知り、国家が国民を煽る軍事行動の限界を見ました。それだけにトルコ国民に抱いてもらえている日本の民間人への熱い想いをありがたく感じました。
トルコの国土は日本の約2倍、人口は約半分、食料は自給しており、広大な手付かずの平野があります。すでに文明発祥の大河をせき止め、灌漑に生かし、麦などの増産に努めていることは初回旅行時に触れた通りです。他方日本は、やがて食糧問題で深刻な事態を迎えるでしょう。その時までトルコとの友好関係をより深めておきたいもの、と思いました。友好的なギブ&テイクの関係が求められますが、その手は多々あるようです。
やがてトルコは、水問題で川下のシリアなどと深刻な事態を迎えるでしょう。その時にわが国は農業指導が出来るのではないでしょうか。農業用水を蒸発などで大量に失う麦作ではなく、より少量の水で済ませ得る水稲技術を伝授してはどうでしょうか。
あるいは、日本を他山の石としてもらう手もあります。やがてトルコは、今日の中国のような国情、拝金主義がはびこる国になりかねません。イスタンブールでの夕食時に見た光景は1960年代の日本で繰り広げられたX’masの夜のようで、消費は美徳に酔いしれ始めていました。日本には多々、学んでもらえる失敗事例がある、と思いました。
このようなことを考えていたときに、日本では中国の空母におののき、軍備強化を叫ぶ古典的な考え方の人がいまだにいることを知り、あきれました。民間人を戦場に刈りたてかねない策や、未来世代に尻拭いを強いかねない策は2度と考えてはいけない、と思いました。それだけに、120年前の日本人の真心に感謝しました。
|
 |
 |
|
東大寺の大柱と比較する話も飛び出し、「はるかに太い」と応えたわけですが、実際の太さは、直径6m。なんと周囲19m近くもあり大人13人がかりでした。太平洋戦争では、同様の誤解(過小評価)が多々あったのではないでしょうか。少なくとも、原爆開発問題では、軍の上層部はこれに似た判断(8月14日当周期「面子とセミの交尾」で触れた)をしています。 |
|
 |
 |
 |
アナトリア(トルコのアジア部分)で最大の隊商宿を見学しました。シルクロード沿いに40km(険しい道程の場合はもっと短い)毎に設けられていました。もちろん隊商宿は、いざというときは城塞のごとくに活かされました。この隊商宿が賑わっていた頃の日本に思いを馳せ、ホームシック気味になっています。妻はシルクロードを主テーマにした人形を創っています。 |
|
 |
 |
|
トルコ風呂も体験しました。とても快適ですばらしい施設です。トルコでは、幼児期を過ぎれば親子でも混浴はありませんし、温泉のように複数の人が入浴する場合は必ず水着をまとう文化だそうです。 |
|
 |
 |
 |
パムッカレの石灰棚。そのスケールは想像をはるかに超えていました。その一帯は12万人ものローマ人が暮らしていた夢の跡でした。その頃の日本に思いをはせ、日本人の真心(今も日本を旅した外国人は、日本の市井で体験する日本人の人情を熱く語る人が多い)を育んだ穏やかな国土を誇りに思いました。 |
|
 |
エフェソスの遺跡。図書館と売春宿が道を挟んでつくられていたとか、奇妙な配置だと不思議に思えたのですが、なぜかその間を地下道路でつないであったそうです。 |
|
 |
 |
|
トプカプ宮殿も見学しました。そこにはいわば大奥もありました。アングルなどの画家が描いた想像画のようなハレムもあったのかもしれません。私たち同胞は、トルコの入浴施設の素晴らしさと、アングルの想像画などから勝手に憶測したのでしょうか、卑猥な施設にトルコ(風呂)の名称を用いてトルコの人たちを侮辱していた一時代があります。おおいに恥ずべきことです。 |
 |
 |
|
 |
イスタブールでの喧騒は、高度経済成長期初期の日本の都会を連想させました。トルコの民主化には、政教分離、文字(アラビア文字からローマ字)の変更、男女同権(女性の民族衣装離れなど)の3本柱がありますが、やがてこれがトルコの人々を暴走させかねない、と心配しました。つまり、工業社会の後追いをするのでは、との心配です。今、最も大切にすべき認識は、工業社会はすでに破綻しており、今日の経済的混乱はその病状の顕在化と睨んでおくことではないでしょうか。 |
|
|