|

|
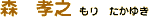

●アイトワのホームページ
●アイトワ循環図 |
|
イスラエルとウズベキスタン 12/04/01
駆け足でイスラエルとウズベキスタンを訪ねてきました。イスラエルは「宗教宗派を超えた世界平和活動」に加えてもらったものです。キリスト教とイスラム教の家庭で育てられた子ども、その教師、そして保護者に集ってもらい、唱歌や折り紙を主媒体にして交歓するプログラムでした。ウズベキスタンでは、かつて訪れた敦煌(中国)やカザフスタンから視たタシケントやサマルカンドにたいする印象を焼き直すことが出来ました。
30日金曜日の夕刻にわが家に帰り着き、ハッピーに吠えられました。ミツマタやシダレウメ、クリスマスローズや菜の花が満開で、ナズナの花が盛りでした。出発前に摘果しておいたダイダイは絞られ、キンカンはジャムなどに煮られていました。ミツバチが27日から動いていたことを、あるいはとても嬉しい知らせが届いていたことも知りました。夕食時に、ノカンゾウのヌタや菜花の煮付けを満喫しながら、エルサレムの随所で自生し、満開だったアブラナ(?)を思い出しましたが、それは沖永良部で見た野生化(?)した十字架植物を思いださせました。やすむ前のマキで焚き上げたわが家の風呂は極楽でした。太陽の光で半ば沸いた天水を用いたそうです。翌朝は雨で明け、午後から除草。
イスラエルは人口の20%がアラブ人で、その8割はイスラム教徒でしたが、エルサレムでは、ガザ地区の騒々しさなど想像できないほど和やかでした。どうやら既成概念のある大人は2重の弊害を抱えており、不幸の再生産に努めるような生き方をしていそうだ、と反省させられました。ウズベキスタンでは、シムダリヤとアムダリアの両大川を越える幸運もあり、人類の行く末が瞼に浮かんできそうな錯覚に襲われました。
旅の始まりはべス・エル社という空気清浄機会社の訪問でした。1000人が働いていましたが、キブツ(共同体)の会社と見てよさそうです。ドイツを主にスエーデン、アルゼンチン、カナダ、オランダ、アメリカ、あるいはスイスなど多くの国々から集ったキブツの職員が、500人のイスラエル人と一緒になって、放射能も除去できる手動可能の機械を生み出し、60カ国に輸出していました。テーブルに並んでいた歓迎の茶菓子などはすべて自家(社)製で、このキブツの自己完結性の高(?)に感心しました。
イエスの遺跡を、漁師のペトロと出会い数々の説教と奇跡で知られるガリラヤ湖をはじめ、囚われの身となる前の1週間を過ごしたゲッセマネの園、最期の晩餐をとった部屋、十字架を背負って登った坂道、あるいは復活した場所など、あらかた訪ねました。もちろん、「死海文書」が発見されたクムラン、ユダヤ人が国として壮絶な最期の戦いをしたマサダの砦、ダビデの墓なども訪ねましたし、死海では体が沈まない怖さも体験しました。
ウズベキスタンは3泊4日でしたが、最終日にはアーモンドや杏の開花や、柳の芽吹きを見届けましたが、春はまだ2〜3日の好天を要しそうに思いました。首都タシケントから、独立するまでは首都だったサマルカンドに向かいましたが、そこでチムール帝国の壮大さだけでなく偉大さにも圧倒されました。130以上の民族やさまざまな宗教を名乗る人たちが住み着いており肩を寄せ合って生活しています。タシケントではソ連時代の街づくりの特色と、当時の重苦しい生き方のあり様が残っていましたが、ロシア観やプーチン観に触れることが出来たようにも思います。とりわけ、ウズベキスタンは6ヶ月の猶予期間をおいてアメリカ軍を撤退させたが、なぜそれが日本にはできないのかと質問され、答えに窮しました。それはともかく、この旅では体重を少し減らせていました。
|
 |
 |
|
ベス・エル社では、放射能も除去できる大小様々な空気フィルタを生産していました。工場には、オヤツに振舞われた自家製ケーキなどの原料となった小麦を貯蔵するサイロもありました。この会社は、テルアビブ空港からガリラヤ湖を目指す道中、エジプトとシリアを結ぶイスラエルでは最初に建設された高速道路沿いにありました。 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
ガリラヤ湖畔でとった昼食は、ピーターフィッシュがメインでした。イエス最初最大の弟子、聖(セント)ペテロでしられる元は漁師の名にちなんでいます。川魚特有の匂いがあり、「ねこまたぎ」の私が、減量の好機とばかりに半ば残しました。ガリラヤ湖畔は砂地と見えましたが小さな貝の浜でした。 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
なげきの壁は、丘の上に巨大な神殿を建設する基礎工事であったとかで、その残された部分も、石組みが3段に分かれていました。元の大きな石組みの上に、ローマ軍に潰された後で築かれた2段があり、一番上の小さな石組みは十字軍の頃に積まれたとか。なげきの壁は屋内のような部分もあります。 |
|

マサダ |

模型 |
 |
ユダヤの偉大な王、ヘロデが増築し、今に残るマサダ(要塞、この写真は雑誌Pen2012.3.1から転載)(とその模型)は偉観でした。幾年もの籠城に耐えられる食料や水の備蓄庫だけでなく、ローマ式の風呂もありました。そのエピソードに、今も変わらぬ人間のおぞましさの一端を見る気にされました。 |
 |
 |
|
 |
 |
|
イエスが最期の1夜を過ごした地下倉庫の上には「鶏鳴教会」が建っていました。そこから、磔刑にされたゴルゴダの丘まで続くヴィオドローサをたどりましたが、イエスが最初に倒れた所では、壁に手のひら大のくぼみがありました。それは、イエスがよろけて手をついた跡で、その後幾多が人でなぞらえているうちに窪みとなったものです。私も手を添えてきました。 |

|

壁に手のひら大のくぼみ |
|
 |
 |
 |
サマルカンドでチムール帝国の壮大さに驚かされた帰路、アフラシアブ(黒い水の川)と呼ばれる細い川の水車で昔ながらに紙をすく工房に立ち寄りました。そこで虹を見かけましたが、東方のわが国とは違って「狐が子供を生んだ」証、と見らていました。さらに西方に行けばどうなるのか、と考えてしまい「ニヤリ」としました。 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
わが家の庭では春が始まっていました。今年になって植えたアーモンドやプラムなどがスクスク育って花盛りになる頃を夢見ながら、イスラエルを振り返りました。イスラエルは植樹率世界1だそうですが、かつてはマツを主に、海外から導入した樹種を植えてきたそうですが、近年はオリーブ、ザクロ、ブドウの3種を主に、イチジクやナツメなど質実な地元樹種に切り替えつつある、とのことでした。 |
|
|