|

|
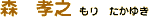

●アイトワのホームページ
●アイトワ循環図 |
|
森とフューチャープル 07/03/11
アイトワ塾の合宿は「イギリスの森」がテーマでした。かつてイギリスは全土(湿地をのぞく80%)が森で覆われていましたが、勤勉なケルト人が多くの森林を農地にしています。シーザー(森を食いつぶした古代ローマ帝国の将軍)がイギリスに足を踏み入れた時に、「北のリスが木から降りずに南の海まで行けるであろう」との伝説が作られています。そのおり、森を信仰の対象とするケルト人が、森をたくみに生かして戦い、シーザーに恐れをなさせて海岸から10マイルしか進軍させていません。その頃すでに森林被覆率は20%程度になっていました。
その後の中世は森林破壊を抑制させています。とりわけ王家は封建制の下に森林法まで定めて森林を守らせています。今日のイングランド王家は、1066年にノルマンディから攻め込みイギリスを征服したウイリアム王に始まっていますが、シカ狩りのための鳥獣保護のために森林を厳格に守らせている。今日の森林被覆率を5%にまで枯渇させたのは16〜17世紀の第一次産業革命です。木材を燃料として大量に必要とした鉄、ガラス、塩などの大量生産を推し進めたためです。近年は復元に努めていますが6%程度にとどまっているとか。ちなみに、今日のフランスの森林被覆率は18%、黒い森(シュバルツバルト)で知られる旧西ドイツで25%程度。わが国は75%です。
こうした話を聞きながら、いろんな想いが交錯しました。森を敬い、工業化に馴染まなかったケルト人への興味が増しました。18世紀にイギリスで始まった本格的な産業革命は、木材から石炭への転換つまり燃料革命との説に対し、理解度を深めました。工業文明では後進の日本が、工業化に成功しながら8割近くの森林に覆われていることに興味を抱き直しました。とはいえ杉や檜の森ばかりに変えてきましたが、この国の政策に応じずに約2000haの照葉樹林を守り通し、今では国のモデルにした人々が宮崎県綾町にいます。この人々への敬意を払い直しました。また、2週間ほど前に嵐山の中腹で唯一生き残っている赤松があったことを思い出しました。
こんな想いにかられながら多忙な一週間を過しました。妻の人形教室展が8日から京都文化博物館で始まり、妻に代って風呂焚きや温室の水やりをしばしば引き受けました。カフェテラスに大きな水鉢を入れ、水鉢は15に増えましたが、それらの配置換えをしただけでなく、8つの掃除を済ませました。小さなアイトワの森を振り返り、この森を生かした循環型生活を一書にまとめる作業にかなりの時間を費やしました。楽しい来客や外出、あるいは嬉しい知らせや興味のある記事に触れたり泊りがけの出張にも時間を割いたりしています。
嬉しい知らせの第1は、かつての顧問会社の中堅幹部から、かつては仕事を作るのに苦労したのに今はこなすのに苦労をしている、との知らせでした。私が推奨した企業の体質転換を計る事業をこの人がその気になって手を出してくれていなければ、この会社にこの喜びを体感してもらえていなかったかもしれないのですから。来客では、東京から家族連れで帰郷した友に立ち寄ってもらえたり、金沢や市内での講演で知り合えた人たちに訪ねてもらえたりしたことです。
興味のある記事の第1は、京都に住む帰化人です。フューチャープル思考の企業経営者で、大震災を織り込んで賃借りしている複数の事務所を高層階から低層階に切り替えていますが、このたび次代を見越して週休3日制を構想してことを知りました。かつて週休5日制の「菜園家族」を提唱する小貫先生を訪ねたり、過日ゴアさんに触れたりしましたが、両者を思い出しました。私は少ない休日を生かし、サラリーマンをしながらその実践に努めてきましたが、それを制度として採用するために率先垂範している企業家がいたわけです。子どものイジメに対する意見はまったく同じでしたから、安倍さんの言う美しい日本の色が、余計に褪せて見えました。
|
 |

|
|
アイトワ塾のあとで、翌朝訪ねた毘沙門天。合宿はある企業の施設を使わせてもらいましたが、そばに立派な毘沙門天があります。桜の名所として、あるいは動く襖絵でも知られるところです。一切経蔵もありました。 |
 |
水鉢の配置換えをし、掃除に手を付けました。メダカとタニシしか入っていなかった鉢には糸トンボの幼虫(ヤゴ)がいました。金魚にとってはご馳走の大きさですから、掃除を済ませた8つの鉢のうち5つにはメダカとタニシしか棲まわせないことにしました。もちろん黒い天然のメダカと、人工のメダカを分けて棲まわせます。 |
 |
樹木ではサンシユが満開です。サクランボの木は満開を過ぎ、梅はほぼ散ってしまいました。サクランボの木は大垣を離れるときにもらった記念樹ですから、報告とお礼を言いに訪ねたかったのですが時間をつくれませんでした。実はこの土日に大垣市環境市民フェスティバルがあり、呼ばれていたのですが、1日を避けなかったのです。 |
 |
 |
|
草花ではクリスマスローズが盛りです。ショカツサイ(ムラサキハナナ)やミニ水仙も咲き始めました。アマナ(右、は日本に自生するチューリップの原種)、タンポポ、ナズナ、ヒメオドリコソウ、オオイヌノフグリ、ハコベ、ホトケノザなどが本格的に咲き始めています。アマナの自生場所を増やすために昨年3箇所に移植しましたが、いずれでも芽が出ています。 |
 |
昨年試みたキンカンの剪定は大成功でした。実も少しは取れそうですし、こじんまりとしたよい樹形にできました。月桂樹の剪定も成功で、よい樹形になりました。 |
 |
それぞれのひな(雛)たち、との人形展はとても賑わっていました。80人の生徒さんが出品されましたが、それぞれ個性や特色、想いや訴えが表われており、とても楽しかった。 |
 |
自然生えのサクラソウ。幾箇所かでサクラソウが自生するようになりました。ここにくるまでに何年の歳月を要したことでしょうか。今年から、日本サクラソウを自然生えするように試みてみようとしています。 |
|
|